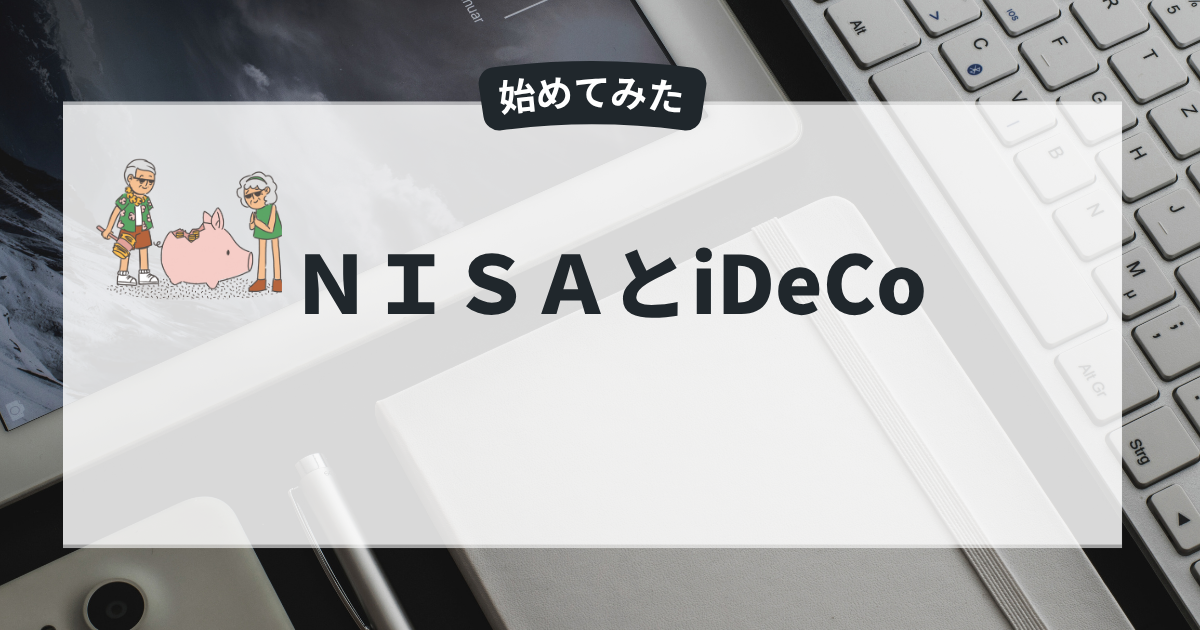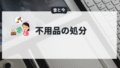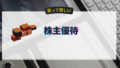口座開設に四苦八苦
NISAとiDeCoを始める為にどこの金融機関がお得なのか?と
調べた結果、「ネット証券」が手数料等について最もお得という
ことが判り、口座開設をしてみました。
今は何でも「YouTube」に説明動画があるので、スマホ片手にパ
ソコンにログイン。「簡単開設10分で出来る!」がうたい文句
だったのに、いざやってみるとスマホの「マイナンバーカード」の
本人確認(証明写真自撮り)でスマホの動きが悪く、四苦八苦しま
した。
結果、「アンドロイド」では「マイナンバーカード」の読込と、自
撮りの連携がうまくいかず、結局「マイナンバー」の提出は郵送と
なりました(簡単開設10分は1週間を要すことに・・・)。
逆に、旧NISAの口座開設の時は金融機関からのお誘いで始めた
ので、「ネット証券」とは違い営業担当者がわざわざ足を運んで説明
してくれて、申込用紙の記入と必要書類を準備して営業担当者に渡せ
ば口座開設が完了するといった感じで特に「四苦八苦」した記憶は
ありません。人を介さないという所が、「ネット証券」の強みで手数
料が安くなっていることなんだなぁ~と思いました。
NISA口座のお引越し(金融機関→ネット証券)
「旧NISA」を金融機関で開始していたので、「新NISA」も引
き続きそのまま延長していました。
当時は、「新NISA」についてもどこでやってもリスクは同じだし
「どんぐりの背比べ」で一緒だと思っていました。
しかし、資産運用の勉強(YouTubeを視聴)をするうちに、手数料や
運用商品のラインナップも各金融機関や証券会社毎で、全く違うもの
だという事を知り金融機関の引っ越しを決意しました。
「新NISA」の金融機関の変更は、現在口座開設している金融機関に
廃止手続きを行い、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」
を受け取り、変更したい金融機関に提出することで完了します。
この手続きは年単位でしか行えないので、私の場合は10月頃に書類
を取り寄せて、翌年から「ネット証券」へ変更する手続きをしました。
その時に1年だけ積立をした「新NISA」の投資信託の扱いにつ
いて金融機関へ確認したところ、積立は継続できないが運用はその
まま「新NISA」扱いで続けることができるということでした。
つまり、運用損益を確定させるまでは積立てた金額は「ネット証券」
で開始する「新NISA」枠【1800万円】から差し引いて管理す
ることになるということを知りました。
iDeCoもしてみよう!
2024年12月から、全ての人が「iDeCo」に加入できるよう
になりました【但し、国民年金保険料を納めていることが条件】。
私も企業型確定拠出年金(DC)と確定給付企業年金(DB)に加入
して正社員として働いていますが、「iDeCo」に加入できるように
なり、残り数年で60歳となる年齢ですが、今から始めた場合のリス
クがどうなるのか知りたくて、開設した「ネット証券」で始めてみる
ことにしました。
ここで、「iDeCo」の商品の購入方法が少し特殊なので説明します。
「iDeCo」は拠出できる金額に対して選択した商品(投資信託等)
の割合を指定する必要があります。
【例】毎月1万円を拠出する場合、これを「外国株式25%」、「国内株
式25%」、「外国債券25%」、「国内債券25%」など自分の決めた割合で
積立購入していきます。
この商品割合を指定するということが、初心者には理解し難いようで、
姪っ子が「iDeCo」を開始する時に配分指定の書類が手元に届いて
いましたが、配分の意味が理解できず放置したままで「iDeCo」の
積立が始まらなかったということがありました。
「iDeCo」が普及しにくいのは、複雑怪奇な制度であることが原因
ではないかと思います。60歳まで引き出し不可ということも足枷かも
知れません。
逆にプラス思考で考えると、手続きさえしてしまえば、完全放置(自分
の状況が変化しなければ)で「長期運用」が確実に行えるといったメリ
ットがあるともいえます。
税金面でもメリットがあり、会社員については年末調整で自営業の方は
確定申告をすることによって、掛金を所得控除することもできます。
この税金面で、私が「確定申告」をしたことで学んだのが、所得税と住
民税はつるんでいるので、課税所得を低くできれば住民税も低くなると
いうことを覚えておくといいと思います。
何故なら、課税所得の約10%が住民税となるからです。
まとめ
「NISA」と「iDeCo」どちらかを始めようかな?と悩んで
いる方は今も多いと思います。「ネット証券」口座をまずは開設して
みてはいかがでしょうか?