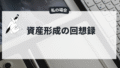年金の種類
国の年金は簡単にいうと2種類存在します。「国民年金」と「厚生年金」です。
「国民年金」は20歳以上60歳までの40年間保険料を納付(満額)で
基本的には65歳から受給できる制度です(資格期間10年以上必要)。
「厚生年金」は会社員や公務員が加入するもので、基本的には65歳から
受給できる制度です。「厚生年金」の保険料には「国民年金」分も含まれて
いて、「厚生年金」に加入している間は「国民年金」の保険料も同時に納め
ていることになります(1カ月以上:受給には国民年金の受給資格必要)。
年金の繰り上げ受給について
年金は基本的には65歳からの受給となりますが、1カ月早めるごとに0.4%
づつ年金額が減額されることを条件に、最短で60歳から受給可能です。
例えば60歳から繰り上げ受給した場合の年金額の算出は0.4×60カ月の
24%減となり【年金受給額×(1-0.24)】で算出できます。(年額)
繰り上げ受給のデメリット
- 国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなること。
- 繰り上げ受給したあと、「障害年金」の受給資格ができた
場合も権利がなくなる。 - 「厚生年金」を受給できる方は、「国民年金」「厚生年金」
を同時に繰り上げすることが必要となることです。
【一度「繰り上げ」請求をすると取り消しすることはできません。】
年金の繰り下げ受給について
年金の繰り下げは65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間で
年金の受給が開始できる制度です。
年金は1カ月繰り下げするごとに0.7%増額になります。
例えば65歳から5年繰り下げ受給した場合の年金額の算出は42%増
になり【年金受給額×(1+0.42)】で算出できます。(年額)
「厚生年金」を受給できる方は「国民年金」と「厚生年金」を別々に
受給申請できます。
例えば「厚生年金」を65歳から受け取り「国民年金」は70歳まで
繰り下げるということも可能です。
国民年金保険料の滞納について
国民年金保険料を滞納すると、さまざまなデメリットがあります。
- 資格期間(10年)を満たないと受給できない。
- 将来受け取る国民年金が減額される。
- 障害年金、遺族年金が受け取れない。
- 延滞金が発生する。条件によっては財産の差し押さえもある。
- iDeCo(個人型確定拠出年金)ができない。
このようなデメリットがあるので、支払いが困難な場合は未納のまま
放置せず、「免除」や「納付猶予制度」「学生納付特例制度」を申請
しましょう(窓口:市区町村役場、年金事務所)。
免除申請し認められた場合は、受給資格期間にカウントされるので放置
した場合との扱いは全く別物です。
国民年金保険料の追納について
国民年金保険料は、20歳~60歳までの40年間(480カ月)に保険料
未納で、納付期限から2年を過ぎると時効となり、さかのぼって納
める(追納)ことができなくなります。
国民年金保険料の未納期間については、誕生日頃に送付される
「年金定期便」で確認できます(ねんきんネットでも確認できます)。
年金受給が近くなると、自分の年金額がいくらなのか?気になります
よね?できれば、国民年金保険料については満額で受給できるほうが
いいと思います。
一般的には、大学卒業後に会社へ就職したため、国民年金の未納期間が
2年(24カ月)だったとすると、この場合の国民年金の受給額は
【国民年金受給額(満額)÷480×(480-24)】で算出でき
ます。
20歳になった時、国民年金保険料の納付書が送付されてくると思
いますが、学生特例制度を申請して就職してから支払う(この場合
追納期間は10年)かそのまま放置すれば、未納期間が発生すると
いうことになります。
未納期間があるときの追納は60歳を過ぎてから、65歳までの間で
任意継続を申請して支払うと、国民年金保険料相当分を追納すること
が可能です。
詳細を確認したい場合は「日本年金機構のホームページ」を確認して
ください。
遺族年金について(納得いかない事)
私の場合、夫婦共働きで会社員だったので、自分の「厚生年金」と
「国民年金」があります。夫が一回り年上なので、年の順番から
考えても私のほうが残される可能性が高いです。そのことを考慮し
年金のことを主体的に考えると、最低でも「国民年金」は5年繰り
下げて受給したいと考えてます。
最近、「国民年金」を5年繰り下げることの条件として、受給権が
発生していないことが前提になることを知りました。簡単に言うと
私が「国民年金」を繰り下げるまでに、夫が死んで「遺族年金」の
受給権が発生すると、私の「国民年金」の5年繰り下げはできない
ということです。
勿論、夫には長生きしてもらいたいと思っていますが、年金のこと
を知り主体性を持って受給したいと考えているので、昔ながらの
制度に言葉を失いました。
あともう一つ納得できないのは「遺族年金」は本来の年金の75%
に減額されるということです。
例えば「厚生年金」100万円を受給していた夫が亡くなった場合、
妻が受給する「遺族年金」は75万円になります。妻はその「遺族年金」
と自分の「国民年金」を受給することになります。
もし「厚生年金」を5年繰り下げして年金を受給していた夫の本来の
年金は繰り下げする前の年金額になります。
例えば65歳での「厚生年金」の受給額が100万円の夫が5年繰り
下げした場合の「厚生年金」の受給額は142万円(年額)。もし夫が
亡くなり「遺族年金」を受給することになった場合の妻の受給額は本来
の年金額の75%になるので、「遺族年金」は75万円になります。繰り
下げ後の年金額の75%ではありません。
今は共働き夫婦も増えてきて、「厚生年金」を納める方が多いと思い
ます。老後の「遺族年金」については自分の「厚生年金」が十分あ
る人には、繰り下げの選択肢が欲しいです。国の年金制度改革法案
に入れていただきたい案件です。
私の場合は高校卒業後、今の会社に就職して60歳まで働くと勤続
42年になります。大学卒業後の夫より数年多く働いてます。
夫の「厚生年金」の75%より自分の「厚生年金」の受給額が高く
なるので、基本的には「遺族年金」より自分の「厚生年金」を受給
することになります。
自分の「厚生年金」については3年繰り下げして、夫の受給額より
多くしたいと考えてます(何となく負けたくないので)。
「厚生年金」の繰り下げもやはり「遺族年金」の受給権が発生して
いないことが条件になります。
あと、もう一つ疑問があります。自営業で「国民年金」しか受給して
ない両親の「国民年金」については、明確な「遺族年金」というものが
無いという事を知りました。
どちらかが他界して一人になった場合の「国民年金」の受給額は一人
分だけになるのか?この件も気になる案件です。
繰り上げ・繰り下げ(我家の場合)
夫が年金を受給できる年齢になった時に、「厚生年金」を受給開始
すれば「加給年金」が受給できるメリットがあったので、65歳
から受給しました。「国民年金」については年金事務所で夫婦喧嘩
になるほど議論して5年繰り下げ手続きをしました。
議論内容:夫【いつ死ぬかわからないから65歳から受給する】
私【国民年金の受給額も満額でないから5年繰り下げして受給】
夫は年金受給を損得勘定で考えていましたが、私の持論は生きてる
ほうが大変で、「死んだら損した~なんて思わんやろ?」という思い
で今後の生活重視で5年繰り下げを提案しました。
まとめ
年金受給は60歳以降生きていく為に、全員が手続きする国の
制度です。生きている限りもらえるお金で生活の基盤になります。
主体性を持って、国民年金保険料を納めて自分の年金を受給でき
るように、頑張って行きましょう!